![開運!なんでも鑑定団【大発見!茶人<千利休>切腹に至る衝撃秘宝に超絶値】[字] …の番組内容解析まとめ](http://shisyou39jp.php.xdomain.jp/wp-content/uploads/2022/06/image-312.png)
出典:EPGの番組情報
開運!なんでも鑑定団【大発見!茶人<千利休>切腹に至る衝撃秘宝に超絶値】[字]
■豊臣秀吉が<千利休>に切腹を命じた理由がお宝に!?…超ド級鑑定額■歴史偉人の手を転々…<徳川慶喜>が贈った名刀に衝撃値■超貴重…2300年前<神秘お宝>に仰天■
詳細情報
番組内容
5年前、骨董好きの父が遺し、7万円かけて表装し直した「松尾芭蕉直筆の句」で出張鑑定に出演したが、結果は真っ赤な偽物。放送後、周りからずいぶん冷やかされた。そこで今回は、父と自分の名誉挽回のため、安土桃山時代の大茶人・千利休のお宝でリベンジしたい!果たして本物か!?
出演者
【MC】今田耕司、福澤朗
【ゲスト】犬童一心
【アシスタント】片渕茜(テレビ東京アナウンサー)
【出張鑑定】第3回武器武具鑑定大会
【出張リポーター】松尾伴内
【出張コメンテーター】高橋英樹
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
鑑定士軍団
中島誠之助(古美術鑑定家)
北原照久(「ブリキのおもちゃ博物館」館長)
安河内眞美(「ギャラリーやすこうち」店主)
奥野保則(「観覧舎」店主)
谷一尚(「林原美術館」館長)
増田孝(愛知東邦大学客員教授)
澤田平(「堺鉄砲研究会」主宰)
柴田光隆(「刀剣柴田」代表取締役)
関連情報
【番組公式ホームページ】
https://www.tv-tokyo.co.jp/kantei/【見逃し配信】
https://video.tv-tokyo.co.jp/kantei/ジャンル :
ドキュメンタリー/教養 – カルチャー・伝統文化
バラエティ – その他
趣味/教育 – 音楽・美術・工芸
テキストマイニング結果
ワードクラウド

キーワード出現数ベスト20
- 万円
- 利休
- お宝
- コイン
- 松尾
- 年前
- 映画
- 結果
- 本物
- アフガニスタン
- バクトリア
- 紀元前
- ホント
- 甲冑
- 自分
- オープン
- ギリシア
- 貴重
- 登場
- 当時
解析用ソース(見逃した方はネタバレ注意)
<本日のゲストは…>
<映画に興味を持ちはじめたのは
小学4年生のとき。
きっかけは たまたまテレビで見た
ビリー・ワイルダー監督の 『ワン・ツー・スリー』。
当時の東西冷戦を皮肉った
大人向けのコメディーでしたが
あまりのおもしろさに
一気に映画にハマり
以来 学校から帰ると
ランドセルをしょったまま
テレビの前に直行し
午後3時からの
< そして 次第に自分でも
映画を作ってみたいとの
思いが募り 17歳のとき…>
<大学卒業後は
CMディレクターとして
広告制作に没頭しましたが
30代になり
部署を異動したのをきっかけに
映画製作を再開>
言わんとこと思ったけど 言うわ。
ああ…。
今日みたいにな
舞台で ヘラヘラしてると
だんだん むなしくなってきて
気分が悪くなってくんねん。
<1995年 女性漫才師の
揺れ動く心の機微をつづった
『二人が喋ってる。』で
長編映画デビューを果たしました>
私ら このコンビ どこまで続ける?
<2003年には
『ジョゼと虎と魚たち』が
単館系の映画ながら
興行収入3億円を超える
大ヒットとなり 芸術選奨
文部科学大臣新人賞を受賞>
いちばん怖いもん見たかったんや。
好きな男の人ができたときに
こうやって。
< その後も
『メゾン・ド・ヒミコ』
『ゼロの焦点』など
数々の話題作を
手がけ
日本アカデミー賞
優秀監督賞を
3度 受賞。
日本を
代表する
映画監督と
なりました。
犬童さんの最新作
『名付けようのない踊り』が
現在 公開中。
世界的ダンサーとして活躍する
田中泯に 2年にわたり密着し
その踊りと生きざまを追った
ダンスドキュメンタリーです>
脳みそに…
海に沈んでいきそうな感じ。
依頼人の登場です。
東京都からお越しの
よろしくお願いします。
ようこそ 「鑑定団」へ。
よろしく どうぞ。 お願いします。
キャンペーン活動?
そうです。
必ず これを着て出てます。
へ~っ!
私 拝見いたしました。
俳優としての田中泯さん
大ファンだったんですけども
ダンサーとしての田中泯さんのこと
よく知らなかったんですよ。
ちょっと衝撃的でした。
畑仕事されたりとか…。
ふだんね。 そうなんです。
もともとダンスをやってて
それでは ちょっと
やっぱり飽き足らなくなって。
自分の表現が?
自分にしかないダンスを探して
畑仕事で作った体で
踊るって決めてる方なんですよね。
ふだん どういう方なんですか?
田中泯さんって。
ダンスのことばっかり
考えてる人ですよね。
僕 最初に会ったのは
日本アカデミー賞の会場で
20mくらい先に泯さんが ただ
座ってたんですよ こうやって。
全然 誰だか
わかんなかったんです そのとき。
ただのおじさんに見えて。
おじさん… はい。
でも ムチャクチャかっこいいんですね。
で ホントに
ものすごい存在感なので
それが どういうとこから
出てくるかっていうの
ダンスを撮影する中で 自分の中で
謎が解けないかなと思って。
へ~っ。
さあ どんなお宝なんでしょうか?
拝見しましょう。 お宝 オープン!
座ってるのが ビリー・ワイルダー。
『お熱いのが
お好き』とか
『アパートの鍵貸します』とか
その方が撮った
『ワン・ツー・スリー』という
映画があるんですね。
先ほど VTRの中であった…。
そうです。
僕が映画 好きになったのが
この映画が始まりなので
20年くらい前に CMの撮影で
ロンドンに行ったときに
すごい有名な古い映画の
ポスターのギャラリーがあったんです。
そこに 『ワン・ツー・スリー』のポスターを
探しにいったんです。
もう日本では
絶対 手に入らないので。
で いかほどだったんですか?
そのとき 8万円くらいですか。
ソール・バスっていう すごい有名な
アートディレクターの人がデザインしてて
映画のタイトルとか
いっぱい作ってる人で。
今 見ても やっぱり
かっこいいデザインですもんね。
悩んでるのが いいんですよね。
ちょっと。
この巨匠が悩んでるのを
ポスターにしてるっていう。
常に仕事部屋にあって
自分の横に置いてあるんですけど。
そうなんですか。
横から ビリーが
いつも見てるっていう…。
ああ 仕事ぶりを見てる?
ちょっと似てきてませんか?
いやいや いやいや…。
三谷幸喜さんが むちゃくちゃ
ビリー・ワイルダーファンなんで
三谷幸喜さんが もし
欲しいって言ったら
相当な高額を
出してくれると思いますね。
ご本人の評価額です。
おいくらでしょう?
10万で どうですか?
三谷さんだったら 大河の脚本
3本分くらいのギャラは たぶん出す。
(笑い声)
まいりましょう。 オープン ザ プライス。
5万円!!
5万。 ちょっと伸びなかったか。
ホントですね。
うん。
このポスターは
映画完成前に使われる
アドバンスポスター
といわれるものになります。
本格的な映画宣伝の
前のものですから
数が非常に少なくて
珍しいものになります。
ビリー・ワイルダーを前面に出すことで
質の高いおもしろさを
表現しています。
当時 大変評判の高かった
ソール・バスのデザインに
よるものですので
芸術作品 美術作品
としての評価も出ています。
ただ ポスターの裏面を
保存目的で布貼りしてる。
欧米では この保存状態は
すごく喜ばれるんですが
日本では こうした
加工されているものは
あんまり好まれず マイナス評価に
なる場合が多いんですね。
いろいろ褒めてもらったわりには
値段は…。
そうなんすね。
(笑い声)
まあね 三谷さんに
売る気もないでしょうから。
聞いてはみたいですよね。
(笑い声)
どうも ありがとうございました。
どうも ありがとうございました。
ありがとうございました。
<続いては 奈良県 奈良市から。
こちらの株式会社 奈良義肢に
お伺いしました。
ごめんくださ~い>
ようこそ いらっしゃいました。
お待ちしてました。
<次なる依頼人は
創業者の…>
<奈良義肢は 瀧谷さんが
1980年に設立した会社で
地元の病院と連携し
患者さん一人一人に即した
義足やコルセットを製作。
昨年 ご子息に
会社を任せたあとも
たびたび作業場を訪れ
サポートしているそうです。
もともと大手義肢会社で
モーレツ社員として働いていた
瀧谷さんが
独立を決心したのは 25歳の時。
技術指導教官として アフガニスタンに
1年間 滞在したのが
きっかけでした>
< そして 26年後の2001年
再び アフガニスタンを訪問。
人生の豊かさを教わった
恩返しがしたいと
<現地で一度に20人分ほどの
型取りを行い 日本で製作>
< しかし現在 アフガニスタンの政情が
不安定なため活動は休止中>
<頑張ってください。
ところでお宝はなんですか?>
< それは25歳で はじめて
アフガニスタンに行った際
何気なく立ち寄った骨董店で
店主に勧められたもの。
値段を聞くと
気軽に買えるほど安かったので>
鑑定よろしくお願いします。
< いったい どんなお宝か
スタジオで拝見しましょう>
依頼人の登場です。
奈良県からお越しの
ようこそ 「鑑定団」へ。
よろしくどうぞお願いいたします。
活動もすばらしいですね。
すばらしい。
アフガニスタンで。
たくさんの方が やっぱり
求められているというか。
子どもたちは軽いので
地雷 踏んでも
爆発しないんですよね。
大人が踏んだら?
そうです 爆発するんです。
埋めるだけ埋めて
やっぱり どこに埋めたか
わかってないんですもんね。
そうです。
アフガニスタン人っていうんですか
どういう国民性だったり。
とにかく
お客さん好きなんですね。
お客さんを大事にする。
それから義理人情を大事にする。
「ランボー」のイメージしかないから。
そうですね。
怖い国なのかなっていうイメージが。
そうじゃないんですね。
そうじゃないんですね。
そんな アフガニスタンで見つけた
2300年前かもしれないお宝 オープン。
お~っ。
バクトリアコインって 福澤さん
聞いたことあります?
いや聞いたことない。
てっきり ビクトリアかなと思った。
ちょうど アフガニスタンのあの辺り。
そうです。
あの国に
紀元前260年くらいから
紀元前50年あたりまで
ギリシア人の
王国があったというので
その当時に作られた
コインらしいです。
これ マジで古そうですね。
ちなみに いちばん最初に
買ったのはどれなんですか?
いちばん左のやつです。 アレクサンドロス。
これがいちばん最初。
勧めてくるんですよね。
これ 古いコインだよみたいな。
そうです。
思わず買ってしまいました。
いくらやったんですか?
たぶん60ドルくらい。
1万8, 000円くらいです。
なるほど。
左から3番目の小さなコイン。
それが いちばん高かったです。
えっ?
150ドルくらいだから
4万5, 000円くらいですかね。
その当時でいうとね。
これ全部で いくらくらい
使ったんですか?
だいたい 75万くらいです。
ご家族の反応は いかがですか?
早く使えるお金にしてと。
使えるお金。
<バクトリアとは 中央アジアの大河
アムダリア中流部の両岸
現在のアフガニスタン北部から
タジキスタン ウズベキスタン トルクメニスタン
イラン東北部を含む地域の
古い名称である>
<紀元前 6世紀頃には
アケメネス朝の統治下において
ヨーロッパと東アジアを結ぶ
重要な交易地として
繁栄した。
しかし 紀元前331年
ギリシア マケドニアの大王アレクサンドロスが
アケメネス朝を破り
エジプトからインダス川に至る
広域を次々と征服。
バクトリアもまた
大王の支配下となった。
征服地の最東端である
バクトリアは 軍事的要衝で
大王は ここに1万3, 000あまりの
ギリシア人を移住させ
軍隊を結成し 一大都市を築いた。
また大王は バクトリアや
バビロンなどの主要都市で
ギリシアの重量単位
ドラクマを用いたコインを発行。
統一貨幣とし
征服地全域に流通させることで
両替の手間を省き
< これは
異文化交流と
融合のためにも
大いに役立った。
コインには 大王自らの肖像を刻んだ。
これは 多種多様な民族が
入り混じる社会で
権力の存在を
明らかにするためであった。
大王の死後 家臣であった
セレウコスがシリア王国を興し
バクトリアもこれに属したが
王が ギリシア人であることに
変わりはなく
その後の為政者たちも
大王にならい
自らの肖像を
刻印したコインを発行した。
そして 紀元前250年頃。
バクトリア総督 ディオドトスが
シリア王国からの
独立を宣言し
< その後
インド北西部を征服したが
この間 内乱が起こり
グレコ・バクトリア王国と
インド・グリーク朝に
分裂することとなった。
紀元前139年。
北方遊牧民の侵攻により
グレコ・バクトリア王国が滅亡。
インド・グリーク朝も
西暦1世紀初頭に終えんした。
バクトリア王国は 千の都市の国と
称されるほど
繁栄したと伝わるが
その実在を示すものは
時折 発掘されるコインのみで
長らく幻の王国と呼ばれていた。
しかし 1961年。
アフガニスタンのアイ・ハヌムで
農民が石灰岩でできた
柱の一部を発見。
これをきっかけに調査を行うと
5, 000人を収容できる
ギリシア様式の劇場や競技場
ペルシア様式の巨大な宮殿などが
次々と見つかり
ここが
バクトリア王国の都市と判明した。
発掘品のひとつ
<小アジアに起源をもつ女神
キュベーレと
ギリシアの女神 ニケが並んで
描かれており
馬車はペルシア風
東洋と西洋の文化が確実に
融合していたことが見てとれる。
改めて依頼品を見てみよう>
<50枚が銀貨 3枚が銅貨。
1枚がニッケル貨。
アレクサンドロス大王の統治した頃から
バクトリア王国が滅亡するまでに
発行されたもので
アレクサンドロスをはじめ
歴代の王の肖像が
ほとんど 網羅されている。
なかでも インド・グリーク朝
8代目の王 メナンドロスのコインには
通常のギリシア文字に加え
インド系の文字が刻まれており
ギリシアとインドの文化融合の証しと
いえよう>
ロマンありますね やっぱり…。
何か一個きっかけでね…。
調査したら…
5, 000人収容の劇場?
ここにあったんだ みたいな。
すごい時代だったんですね。
手作業ですもんね。 すごいですね。
完全な円じゃないところが
味わい深いですね。
リアルですね。
ご本人の評価額です。
おいくらでしょう?
300万と言いたいですね。
300万で… わかりました。
まいります! オープン ザ プライス!
さぁ 2300年前か…。
おぉ!
うわっ すご~い! 400万!
いや~ すごい すごい!
夢がある。
紀元前3世紀くらいから
紀元前1世紀くらいまで。
バクトリアで流通した コイン…
間違いない。 すばらしいコレクション。
いちばん高いのは
アレクサンドロス大王のコインです。
製作地がわかるんですよね。
バビロン産… 交易が盛んだったので
バクトリアにも流通してる。
アレクサンドロスはギリシアの伝統に従って
獅子の皮をかぶるんですが
インド北西部を征服した デメトリオス…。
象のヘルメット かぶってるんです。
ほう…。
メナンドロス王のコイン…
イランとギリシアとインドと
3つの文化が融合した
コインになっていて 大変 貴重。
バクトリアの歴史については
文献に残ってないので
どういう人が王になっていたか
なかなか
わからなかったんですが
こういった 潰れたコインのコレクションを
読み解くことで
だんだん
わかるようになりました。
第一級の貴重な資料。
わぁ すごい!
いかがですか?
いや うれしいです もう…。
なんか… なんか
認められたみたいな…。
貴重なもの
ありがとうございました。
ありがとうございます。
<戦乱の世に大いなる力を
発揮した 刀 鎧兜 そして鉄砲。
これらは今日 日本を代表する
美術品として高く評価され
特に 刀は 若い女性たちを魅了し
一大ブームを巻き起こしている。
そこで…>
<本日の鑑定士は…>
もう 英樹さんはね 刀とか…。
見るのが好きで…。
刀剣の展示会は
しょっちゅう 行っております。
へぇ~。
< まずは 刀好きが高じ
居合道を始めた…>
何歳くらいから始めたんですか?
広島に…。
専門学校があるんですか?
はい。
ほう…。
<得意なのは 巻藁斬り。
精神を統一し
一気に刀を振り下ろす。
おみごと!>
あれ 難しいんですよね。
シャッて斬るのは…。
そうですね。
< お宝は
南北朝時代の備前の刀工…>
<20年前 なじみの刀剣商から
犬養毅が持っていた名品と
勧められ…>
退職金をつぎこんで 買いました。
850万!?
はい。
政光… まぁ…。
< しかし その後
知り合いの刀剣愛好家に
自慢げに見せたところ…>
1回 返したんですか?
はい。
< しかし その4年後
たまたま開いた
明治時代の文献に
この刀のことが
紹介されており
ビックリ。 それによると
もともとは 榎本武揚が
15代将軍 徳川慶喜より
拝領したもの とのこと。
そこで
慌てて 刀剣商のもとへ行き…>
(松尾)え~っ!
2度目 買ったときは…。
ちょっと お安くなったんだ?
はい。
いろんな方が持たれてる…。
そういう方たちが持つ
刀っていうのは
やっぱり 名刀は多いですから。
<本人評価額は
買い戻した金額 830万円。
刀剣商の話によれば 犬養毅は
選挙資金を捻出するため
これを手放したらしい。
果たして 結果は!?>
ジャカジャン!
<ダウンするも大健闘!>
政光の本物です。
今から 640年くらい前…。
至徳の年季が入っている と。
南北朝の後期になりますとですね
不思議なことにね
ちょっと
小振りになってくるんですよ。
で この刀もね
ちょっと小さい。
そういう点では
おそらく 銘ものでもですね
ちょっと 値段がですね
下がっている という…。
いいとこにあって
大事にはされてきた刀には
もう 間違いございません。
<続いては
自作の甲冑を着て登場…>
すごいですね!
はい。
これ いわゆる 手作りですか?
これ 手作りです。
実は これ…。
叩いて 1枚の板から
こしらえていくんで…。
(松尾)はぁ~!
<故郷の和歌山県九度山町は
真田幸村が長年暮らした地で
12年前 町おこしのため
自ら 隊長となり
手作甲冑真田隊を結成した>
< そこで生み出したのが
アルミ製の甲冑。
水道工事会社を経営するかたわら
1年かけて製作。
軽くて安価に仕上げるために
工夫を凝らし
兜は 工事作業用ヘルメットを。
飾りには タワシを使用した。
この甲冑を着て 仲間とともに
各所のイベントに参加している>
街をずっと歩いて…
気分 どうですか?
めっちゃ…。
< お宝は…>
<10年ほど前 甲冑作りで
試行錯誤していた際
知人に 参考になる
よいものがある と言われ
見せてもらった。
通常の甲冑と違い…>
(松尾)これ 軽いの?
軽いんです。
ちょっと いいですか…
すみません。
あっ… あっ ホントだ!
軽い鎧を作るっていうのは
どういう人たちが作ったのかな?
あっ はいはい 忍 入ってる。
忍者が着てた!?
< これは珍品に違いないと
無理を言って
80万円で譲ってもらった。
本人評価額は
買ったときと同じ 80万円。
実は この甲冑にヒントを得て
軽いアルミを素材にしようと
思いついた。
果たして結果は?>
(松尾)ジャカジャン はい 120万円!
< やった~!>
(松尾)おめでとうございます!
ありがとうございます。
鉄砲伝来頃に作られた
当世具足といわれるタイプの
甲冑なんです。
制作は おそらくは
江戸中期以降。
数百年たっておりますけれど
まるで今日 作ったように
すばらしい保存です。
小手の部分に少しだけ
金属部分がある以外は
全部 皮です。
おそらく重量は
鉄製の当世具足の
5分の1くらい。
しかし鉄砲玉も
跳ね返すような強さで
胸当てにあります小札の部分は
本小札といいまして
一つ一つが
手作りでつないであります。
こういったものは大変 手間が
かかりまして 高級品です。
(松尾)これ 忍者の 「忍」…。
私は信じますね。
忍者の中には
上忍 中忍 下忍という
位があるんです。
上忍であれば
このような甲冑を使ったかと…。
珍しいもので よく
見つけられたなと思います。
<続いては 趣味で
ネット小説を書いている洋夏さん>
何ていうタイトルですか?
「武公の刀」。
題名で書かせていただいてます。
どういう話なんですか?
それは。
< もともと宮本武蔵が大好きで
その生涯について
独自に調べていたが
自分が学んだことを
形にしたいと
2年前 史実をもとにした
歴史ミステリー小説を書き始めた。
それが おもしろいと評判になり
閲覧数は6万回を突破。
現在 サイト上の
部門別 年間ランキングで
第4位となっている>
好きな方 多いですよね。
宮本武蔵さんっていうのはね。
意外と皆さん 知りたい…。
< お宝は こちら>
(松尾)え~っ!?
<日頃から宮本武蔵に
まつわるものを探しており
これは6年前
インターネットオークションで発見した>
海鼠透鐔というのが
おそらく いちばん有名な。
もう1つ…。
まさに それですね。
< どうすれば瓢箪で
鯰をとらえられるかという
禅の問答に材をとったもの。
禅の修養を積んだ
宮本武蔵らしい作で
実は 本物が
武蔵資料館に展示されている。
以前 それを見たことがあり
そっくりだったため
迷わず5万円で落札した>
おそらく出品の方は
たぶん そんなの知らないと。
5万円で このロマンを買えたら
いいじゃないですか。
<本人評価額は 堂々の100万円。
武蔵に憧れ
剣術道場にも通ったが
二刀流は会得できなかった。
果たして結果は?>
(松尾)ジャカジャン 2万円!
< う~ん 残念!>
コピーですね。 鐔というのは
何代も いろんな刀に
はめられていると
その間に少しずつ
摩耗していくんですけども
この鐔はですね
削れてる雰囲気がない。
新しく作られたものだな
ということが わかります。
あと鯰のヒゲが ホニャホニャッて
こうしてるんですがね
本物といわれてる鐔
よく似てるんですけども
そこが鋭いんですよ。
晩年に武蔵は 芸術のほうに
興味があったから
自分の武器 武具を
作ってるんですよ。
ただ それだけに
コピーが多いもんですからね。
<続いては 大垣城鉄砲隊に
所属している若原さん>
何か きっかけはあったんですか?
鉄砲隊に入ろうっていうのは。
武器 武具が好きで…。
<美濃国大垣藩に伝わる
田付流砲術の伝承を目的に
仲間たちと お祭りなどのイベントで
空砲を撃ち鳴らす演武を
行っている>
やっぱり ちょっと
気持ちがいいなっていう。
ワーッて言われるのが。
注目 浴びて もう…。
< お宝は こちら>
原始銃?
はい。
< もともと馴染みの骨董商が
大事にしていたもので
何度も売ってほしいと
お願いしたのだが
売り物ではないと断られ続けた>
結構 通ったんですか?
それは そのあと。
えっ!?
そのときに やっと…。
はぁ~!
< ついに
60万円で譲ってもらえた。
どこが そんなに
気に入ったのかというと…>
1本っていうのは
写真でも見たことあるんですが
2本っていうのは
見たことなかったもんですから。
(松尾)3つあいてる!
ですから連発銃かなというのも
あるんですが… 6連発ですね。
それも珍しいと思うんですね。
初めて見ましたね。
<本人評価額は
買ったときの2倍 120万円。
購入後 いろいろ資料を調べたが
同じものは
ひとつも見つからなかった。
大珍品か?
それとも真っ赤な偽物か?>
<30年間 骨董店に通いつめ
60万円で譲ってもらった原始銃。
果たして結果は?>
(松尾)ジャカジャン ピッタリ 120万円!
< やった~!>
すばらしい!
原始銃といわれる
鉄砲のまさに先祖ですね。
14世紀の初め頃に明朝で
開発されたものなんですが
これは お隣の国の
李朝のものですね。
文字が たくさん書かれてる。
双眼 いわゆる
2連銃のことですね。
火を入れる穴が
6つありますから
六穴と
書かれてあるんです。
1本の銃身に
火薬 玉 火薬 玉 火薬 玉。
3発 込めます。
各火薬の間にはですね
火が移らないように革か紙。
それから前から順番に
撃っていくわけです。
確かに6発 撃てます。
鉄砲というのは1発しか
撃てないのが多いですから
ハイテク銃といえると思います。
後ろに差し込み口があります。
槍のように柄をつけて
使ってた鉄砲です。
ですから 命中精度はありません。
型に流して作りますので
相当たくさん
あったはずなんですけれど
ほとんど今 残っていない。
そういう珍しい貴重な鉄砲です。
<最後は
二匹目のドジョウを狙う七條さん>
二匹目のドジョウっていうことは
どういうことですか?
えっと 3年前にですね 小さな…。
<七條さんが登場したのは
3年前のこと。
お宝は 津田越前守助廣の
脇指でした>
こんなの
何とかしろと 危ない 危険な。
で 親父もう年やろと
もう断捨離せえと。
仮にですよ 息子さん これが
ものすごい高価なものだったら
どうされますか?
すぐ売ってください。
いかほどで購入されたんですか?
当時ですね 3万5, 000円くらい。
それはないわ! あつかましい!
< しかし 結果は なんと…>
400万! おめでとうございます!
どや~!
どや~!
(拍手)
すごかったですね じゃあね。
ビックリしました ホントにビックリしました。
そのあと どうでした?
(笑い声)
あっ もっとね。
(笑い声)
< お宝は 江戸初期の刀工
えぇ~!
(松尾)えぇ!?
それのお父さんっていうのは。
(松尾)わっ すごい!
< こちらも 20年ほど前
シドニーのアンティークショップで見つけたもの。
前回出品した
脇指を入手したのち
どうしても
大小そろいで持ちたくなり
10万円で手に入れたが
実は 家族には
買ったことすら言っていない>
えっ!?
出そうと。
なんとかさ…。
<本人評価額は
期待を込めて50万円。
20年間の隠しごとを
打ち明けることができて
スッキリした!
結果もよければ
言うことなしだが
果たして 結果は!?>
(松尾)ジャカジャン!
100万円!
< これは すごい~!>
うれしい。
すごい!
めちゃ うれしい。
本物に間違いございません。
江戸時代の刀
私どもは 新刀というふうに
言うわけなんですけども
この国定という人は
大阪新刀の祖。
たいへん覇気のある刀を
多く作りまして
ただ長さが短くされてるんですね。
元は 75~76センチあったと思います。
軍刀拵えという第二次世界大戦に
持ってったときの
拵えがありますので
そこに合わせるために
短くしたのかもしれない。
もし 元のままの
長さで残っておれば
この値段の倍。
今のね シドニーの話聞くと
いや もうたいしたもんですね。
うらやましいですね。
<武器武具鑑定大会>
<続いては 滋賀県 東近江市から。
庭にたたずみ 満足そうに
笑みをたたえる この方が
次なる依頼人>
<愛おしげに
見つめているのは…>
< えっ!?>
私
ホントに…。
<住井さんは 滋賀県で代々続く
< もともと この庭は
父 鐵造さんが
手入れしていたのですが
7年前に他界。
代わって
庭の管理を始めたところ
急に苔の育成が楽しくなりました。
その魅力は?>
そういった意味では…。
< というものの
苔の負担にならないよう
毎日 ピンセットで雑草を抜いたり
苔の種類に合わせ硬さの違うホウキで
落ち葉を掃いたり
並々ならぬ
手間と愛情を注いでいます。
その甲斐あって 庭の苔たちは
順調に育ち
1年前の庭と比べると
ずいぶん青々としてきました>
< これからも頑張ってください。
ところで お宝は何ですか?>
実は 私 このお宝で…。
<5年前 住井さんは
滋賀県 湖南市の出張鑑定に出場。
お宝の松尾芭蕉直筆の句は
父の遺品整理の際に
発見したものでした。
本物と信じ
結果は なんと…>
1, 000円!
< これを見た仕事場のスタッフは…>
< とんだ赤っ恥をかいたのです。
そこで…>
鑑定 よろしくお願いします。
<果たして リベンジなるか!?
スタジオに登場です!>
依頼人の登場です。
滋賀県からお越しの
ようこそ 「鑑定団」へ。
よろしくどうぞ
お願いいたします。
いや~ でも立派なお庭で。
すばらしい。
簡単やっておっしゃいますけど
結構 大変じゃないですか?
時間がかかります。
敷き詰められた苔の
あのモフモフ感っていうんですか。
なでたくなるね。
今回は リベンジで来たと。
そう。
じゃあ どういったものか
ちょっと拝見しましょうか。
お宝 オープン!
同じようなものがきました。
さあ これは何でしょう?
千利休の書簡です。
いやいやいやいや。
ご無体な。 ビッグネーム好きですね。
父が遺したメモがあったんですよ。
利休が ある方から
茶壺を欲しいと言われて
用立ててほしい というような
内容だっていうのは
そこに書かれてるんですよ。
確かに利休とは
書いてあるんですよ。
どこに書いてあるんですか?
むちゃくちゃ怪しく
あとから書いたようなとこに
あるんですよ。
ヤバくないですか この位置。
なんで こんなとこに急に
とってつけたように 「利休」って。
いや でもやっぱり
表具はね 雰囲気ありますし。
表具は そりゃ 松尾芭蕉も
雰囲気はありましたよ。
今度は 字は やっぱ風格が…。
箱も やっぱ
2重になってるじゃないですか。
最初から
やっぱり この立派な箱には?
いや それが…。
えっ? あとからですか?
見つけたときは ちっちゃめの箱に
収まってたんです。
この桐箱1つでは ありえないと。
いくらしたんですか この箱は?
ちょっと9万くらい。
高いな。
いや でも
本物やったらすごいですね。
はい ありがとうございます。
いや まだですよ まだ。
<千利休は 安土桃山時代
侘茶を大成した茶人である。
1522年 堺で生魚を商う
商家に生まれる>
<少年時代から 茶の湯に親しみ
19歳のとき
茶人 武野紹鴎に師事。
その修行時代の逸話が
残されている。
ある日 紹鴎は 自らきれいに
掃き清めた庭に与四郎を呼び
掃除するよう 命じた。
すると 与四郎は
しばらく考えたのち
<自然の趣を演出。
美に対する非凡な才に
紹鴎は感嘆したという。
その名が
広く知られるようになったのは
50歳をすぎてから。
織田信長の茶頭に
抜擢されたことが
きっかけであった。
信長は当時
町衆の間で流行していた
茶の湯を自らたしなむ一方
これを政治に利用。
御茶湯御政道と称し
戦で武勲を挙げた配下にのみ
茶会を開く許可を与え
茶道を正式な武家儀礼とした。
また 商人たちが収集していた
茶道具を
強制的に買い上げる
名物狩りを断行。
茶の湯で
権力の集中を図ったのである>
<信長が 非業の死を遂げると
代わって天下人となった
豊臣秀吉も
利休を 茶頭として重用。
秀吉の関白就任を記念して
京都御所で開かれた
禁裏茶会において
正親町天皇に
秀吉が献茶した際…>
<利休の号は
このとき下賜されたもので
64歳にして
天下一の宗匠となったのであった。
では 利休が大成した侘茶とは
どのようなものだったのか。
それは 空間を極限まで
そぎ落とすことにより
緊張感を生み 簡素静寂の中で
もてなす客と
無言の会話を
交わすというものである。
そのため 利休がしつらえた茶室
待庵は わずか2畳。
出入り口は 体をかがめ
頭を下げなければ通れないほど
小さくした。
いわゆる にじり口で
武士といえども
帯刀したままでは入れない。
地位や名誉など
俗世のことはすっぱりと忘れ
無我の境地で
茶を味わってほしいとの思いが
込められていた。
利休は まったく新たな茶道具も
創案した。
その象徴が 長次郎に作らせた
楽茶碗であろう。
ろくろを用いず 手びねり
へら削りで成形したもので
作為がなく 実に素朴である。
竹花入を用いたのも
利休が最初で
この 『園城寺』は
自ら竹を切り出し
作ったものだが
大きなひび割れさえ景色とした。
高価な名物を
ただ やみくもにありがたがる
既成の価値観を否定し
身近にある雑器の中にこそ
不完全の美を
見出したのである>
<天皇や秀吉がくぐる
大徳寺の山門の楼上に
雪駄を履いた利休の木造が
安置されていたこと
また 不当な高値で
茶道具を売買したことが
罪状とされるが
真相は 今なお不明である。
改めて依頼品を見てみよう。
千利休の書簡である。
「急ぎ申し上げます。
知り合いに
茶が四斤か三斤半ほど入る
渡来の壺を欲しい方がいます。
金子十枚でも十二~三枚でも
よいものが欲しいとのこと。
茶事の前なので急いでください。
もう一つ 金子五枚ほどのものも
所望しています。
これも渡来のもの とのことです」。
宛名が切り落とされており
誰に送ったかは不明であるが
知人のために 茶道具の用立てを
お願いする内容である。
利休の号が使われているため
64歳以降のものか>
おっしゃるとおり 内容が
ホントに 利休が
書いた手紙じゃないですか。
そうです。
ねっ。
はい。
これは リベンジ
ありえるんじゃないですか?
1, 000円先生 俺は応援しますよ。
1, 000円先生ですか。
え~!
言うてきたんですか スタッフとか
近所の人には
今日行ってくんでって。
私と家内だけ。
2人だけの秘密。
秘密。
結果しだいで
見てやって言うんでしょ?
ご本人の評価額です。
おいくらでしょう?
100万円で。
今度こそ!
まいります オープン ザ プライス!
さあ ご覧ください。
さあ どうぞ。
さあ 続け ゼロ!
2!
やった~!
(2人)1200万!
本物 本物!
おめでとうございます!
え~!
利休の本物!
松田さん もう
冗談はやめてください。
(笑い声)
マジですか!
私が これまで見てきた
利休の手紙の中でも
最も出来栄えのいい
手紙だと思います。
線がしっかりしてて
そして花押の形も
非常に しぜんに書かれてる。
で 名前の位置が
ちょっと窮屈なんですけども
本文が長くなってしまったので
その位置に書かれてる。
利休の晩年のものですね。
渡壺 フィリピンとか
ルソンとかで作られていた
生活雑器だったんですけども
千利休が これは葉茶壺として
使えるということで
非常に貴重な茶道具として
大名たちが争奪戦をするくらいの
人気が出たと。
金子十二~三枚出しても
欲しいという人が
いるんだということはですね
今でいうと
400万 500万
あるいは それ以上の値段が
つけられている
可能性があるんですね。
利休が吊り上げたんじゃなくて
利休が目利きをしたものだったら
欲しいんだと。
そういう状況が
この手紙では 非常によくわかる。
大切にしていただきたいと
思います。
処刑の原因になった証拠でっせ。
箱作っといてよかったですね。
もうちょいええ箱にしましょうや。
じゃあ もう1個作ります。
3つ?
3つ。
いやぁ ホントに
おめでとうございました。
貴重なもの
ありがとうございました。
ありがとうございました
おめでとうございます。
< お宝鑑定希望の方
お宝を売りたい方は
お宝の写真とエピソードを添えて
ご覧のあて先まで
どしどしご応募ください。
お待ちしています。
詳しくは番組ホームページを
ご覧ください>
Source: https://dnptxt.com/feed/
powered by Auto Youtube Summarize







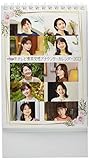


![あしたが変わるトリセツショー「カビ一掃!“かくれカビ”を根こそぎ撃退新対策」[解][字]…の番組内容解析まとめ](http://shisyou39jp.php.xdomain.jp/wp-content/uploads/./wp-content/plugins/rss-make-antenna/no_image.png)
![坂上&指原のつぶれない店★一流社長が立て直したあの店は今!衝撃の展開が[字]…の番組内容解析まとめ](http://shisyou39jp.php.xdomain.jp/wp-content/uploads/2021/09/image-349.png)
![インタビュー ここから「歌手 五木ひろし」[字]…の番組内容解析まとめ](http://shisyou39jp.php.xdomain.jp/wp-content/uploads/2021/08/image-51.png)